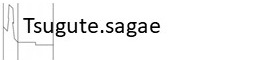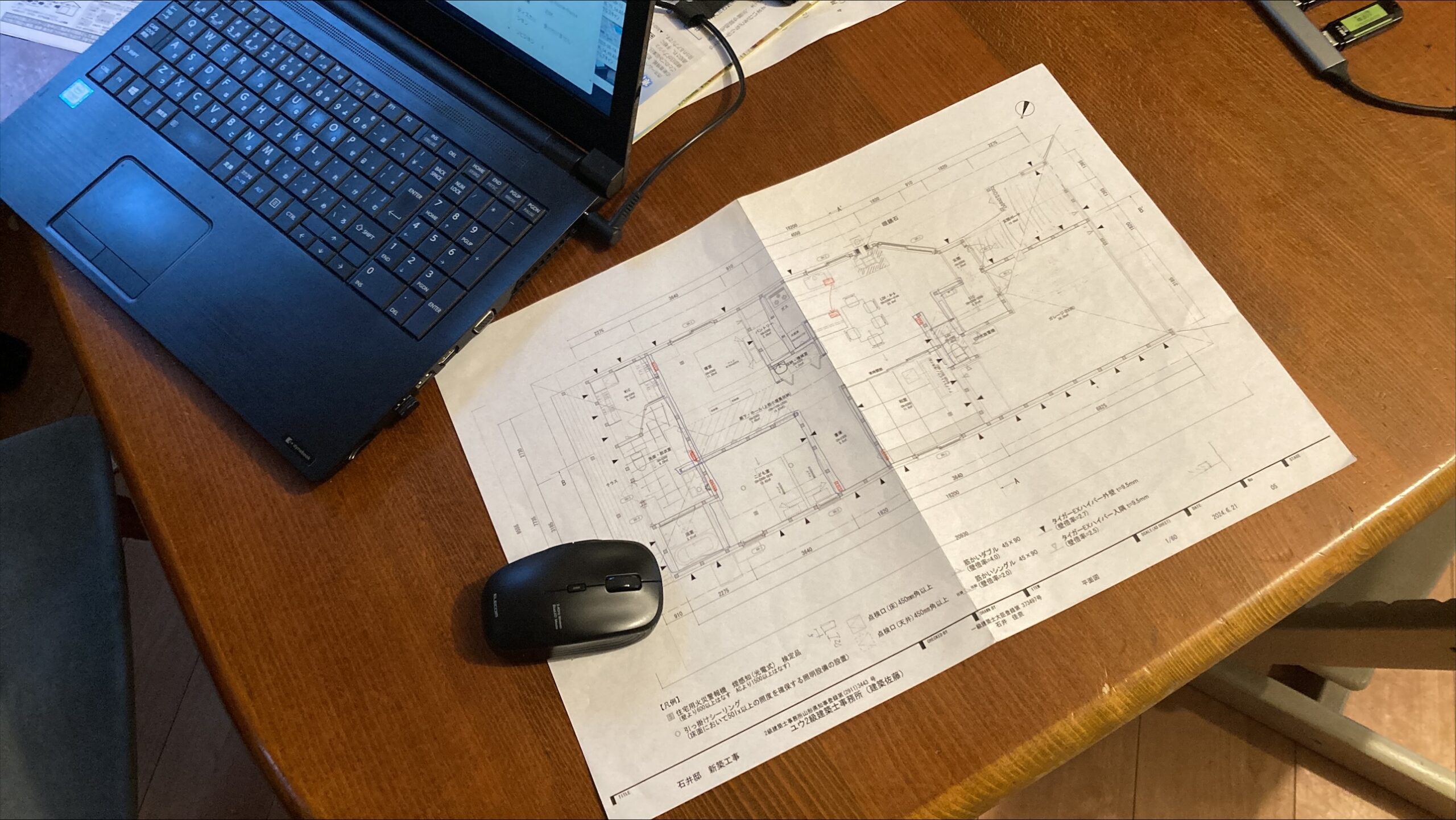計画の時には修繕の計画も立てる
こんにちは、Tsugute.sagaeの石井です。今日は永く家を住み続けるため、修繕性について書いていきたいと思います。今では長期優良住宅の申請時に修繕計画を提出しなければならなかったり、事前の修繕計画の検討も以前よりは重要視されるようになってきたと思います。私が働いていた設備メーカーでは、製品開発を手掛ける際には企画段階から必ず「コンパチ性」についての検討を行い、何かしらの見通しが立たない(見通しがかなり甘い事も多かったですが)と開発はスタートしませんでした。
コンパチ性を考える
コンパチ性を検討するとは「コンパチブル(compatible):互換性のある」の派生語で、互換性がどれだけ容易かを考えるという事です。この考え方はモノを長く使い続ける上でとても大切です。なぜかというと住宅は50年から100年は使い続ける物であり、その間どこも壊れないことなどあり得ないからです。そのため壊れた際にどう直すかというのは、当然住宅にとっては必要な考え方です。住宅では昔からこの考え方はありましたし、考え方としては寒河江市役所を設計した黒川紀章さん等が提唱した「メタボリズム建築(新陳代謝を行う建築)」とも通じる部分が多いと思います。一方でローコスト住宅が多い建売などではこの辺りの考え方が足りていない住宅が多いように感じます。
そのものを修繕する
また修理でコンパチ性の高いものといっても、修理の仕方にもさまざまあります。例えばそのものを部分的に修復するもの。一部の部品を交換するもの。機器や仕上げをまるまる交換するもの等です。当然、使い続けていく上で財布にも環境にも優しいのは、部分的に修復できるものです。例えば、木造でも接着剤を使用しない無垢材の床を採用すれば、傷が付いたり、一部が汚れたり壊れたりしてしまっても、削ったり、一部分を修復する事で永く使い続ける事が出来ますが、クッションフロア等のビニル系の素材を使うと、汚れた部分は数年で貼替えが必要になり、またその時のゴミの量や揮発する接着材の量はそうとうな量となってしまいます。
そのものを取り換える
ただモノによってはそのもの自体を取り換える必要があります。その代表例が設備機器です。設備機器はトイレや給湯器、エアコンなどの事ですが、これれらは修理部品についてもメーカーが10年程度しか保有しておらず、どんなに頑張って使おうと思っても、メーカーサービスから断られてしまって、永く使えないため、結局、そのもの自体を交換する必要が出てきてしまいます。海外では、ホームセンターにエアコンの部品毎に販売していて、どのメーカーもある程度は規格品で、街角で売っている汎用部品で修理が可能だといった話を聞いた事がありますが、偏見かもしれませんが、日本の国内メーカーはしっかり客を囲い込むため、新品を買わせるため、どんどん複雑に、他メーカーとは別の規格を使用して開発しているため、そのものを取り換える以外に私達一般消費者に残された道はありません。
交換品はシンプルさを考える
これは多少しょうがない事という事で我慢していますが、ここで必要になるのがシンプルさです。交換や修理を考えた時に、複雑になればなる程、交換や修理の難易度は上がりますし、世の中に少ないものはどうしても手に入り難くなってしまいます。例えば各ハウスメーカーで取り扱っているダクト式の全館空調は交換しようとすると、その施工や機器の複雑さから数百万円するような製品となっています。一方、私の家で採用した、ルームエアコンを活用した全館空調は、ダイキンの一番シンプルで廉価なシリーズのエアコンを採用したため、高額な全館空調と同様の効果を得ながら、交換する際には10万円かからないぐらいで取り換える事が可能だと思います。エアコンは上位機種になるとセンサーやお掃除ロボット付き等多くの機能が付いてきますが、電気エネルギーから熱を作る効率はほとんど変わりませんが、高機能な分壊れやすくなりますし、お掃除付きのエアコンにしてしまうと、通常料金でのハウスクリーニングが受けられなかったり、マイナス面も多いと感じています。エアコンや給湯器等、住宅設備に関して言えば、なるべく複雑なものは避け、シンプル何ものにしておくという事が、家計にもコンパチ性にも優れているように感じています。
最後に
今日は住宅計画時点で修繕性を検討する事の重要性について書きました。修繕性を加味すると、住宅はある程度シンプルであるべきだと考えています。それは複雑にしてしまうとそれだけ把握や修理といった観点で、住手の実力を超えてしまい、管理が行き届かない状態(=オーバースペック)に感じてしまうと思うからです。シンプルな住宅やシンプルな設備を使う事が修繕性の高い建物にもつながるし、生活にとっても身の丈に合った暮らしが出来る様になり、結局、幸せな時間を生みだすことにもつながっている気がしています。必要最小限のシンプルな暮らしを目指したいものです。今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。