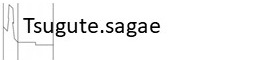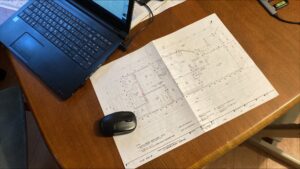快適な空間とは
こんにちは、Tsugute.sagaeの石井です。今日は湿度について書いていきたいと思います。私の考える快適な空間とは、快適な空気の質が欠かせないと考えています。空気の質についてとても重要になってくるのが、温度・湿度・換気の3つです。
空調で全ての空間が同じ温度でも快適ではない
私の家はエアコンを使って全館空調のように、全ての部屋を快適な温度にするようにシステムを組んだので温度は丁度良い温度が全ての部屋で感じられるようになっています。ただ全ての部屋が同じ温度でも「快適な空間」と感じるためには湿度のコントロールが欠かせません。
近年増加傾向の化学物質過敏症(MCS)
近年では接着剤や樹脂、洗剤や芳香剤等の化学物質に過剰にアレルギーのように反応してしまう「化学物質過敏症(MCS)」というものが増加傾向にあります。この原因は、主に過去にかなり大量の化学物資に接触し、急性中毒症状が出現した後の場合か、または有害な化学物質に長期にわたり接触した場合とされているため、日常で化学物質を吸い続ける事が発祥の原因になる可能性があります。ホルムアルデヒドなどの特に有害な揮発物質については、日本も規制していますが、多くの化学物質は規制の対象に入っていません。また近年、特に住宅の高気密化が進む中で、建築基準法では24時間、1時間に0.5回、家の空気が入れ替わる0.5回換気というものを義務付けられています。そのため換気は法律上必須の設備となっています。しかしこの日や季節によって大きく変わる湿度を吸排出してしまう「換気」がより湿度管理を難しくする要因となってしまっています。
湿度の設計
そこで自宅の設計に当たっては、温度に合わせて、換気と湿度をコントロールする設計についても検討を重ねました。目標としては夏場摂氏26度で湿度60%。冬場は摂氏20度で40%です。そこで採用したのが、換気の設備としてあまりメジャーではありませんが、顕熱型の熱交換換気システムと除湿、加湿の対策を入れる事でした。かなりアナログな仕組みが多いので笑われてしまいそうですが、私の中では安価で効果の大きい仕組みもあるので、大きく分けて以下の3つを紹介します。
1、顕熱型熱交換換気システム
顕熱型というのはトイレやお風呂の水周りからも熱交換を行いながら換気するシステムです。これによって、夏場は熱交換で除湿された空気が入って来る。冬場は乾燥が進むものの、換気以外の場所から湿度が逃げていかない状態となります。
2、夏場の除湿はエアコンで
様々な方法を検討しましたが、最も効率的に水分を取り除くことが出来るのは、ヒートポンプ式のエアコンや除湿器です。そこで、エアコンのドレン勾配を1/50程度でしっかり保った上で、結露水がしっかりドレンに流れる様(熱交換器からの滴下を促すため)弱風の冷房運転を行っています。特に今年の夏場は雨続きだった日も多かったので、併用してヒートポンプ式の除湿器も使っていました。
3、冬場の加湿はお風呂と水道で
一つ目はかなりアナログな方法となりますが、お風呂にⅢ種換気扇をつけて、その排気を全館空調の吸込み口の近くに設けました。これによって、冬場にその換気をONにしておけば、お風呂の湿気を各居室に送る事が可能です。もう一点は全館空調のように利用している床下エアコンと顕熱交換機の居室内への取込口(SA)が付いている部屋(自宅では“機械室”と呼んでいます)にフラッシュシンクを設けました。推薦とシンクに空間上がるため、加湿したい時には、ここにタオルをかけてちょろちょろ水を流します。このタオルに顕熱交換機の取込口(SA)から出てくる風が当りタオルが自然乾燥する事で加湿を行います。その加湿された空気は床下エアコンで空調され各居室に運ばれるというシステムです。なかなかアナログな方法ではありますが、初めて住んだ今年の冬は湿度30~40%程度に保つことが出来、誰も風邪をひかず、カビも無く、とても快適な冬を送る事が出来ました。
最後に
ただ今年はまだ基礎から水分の蒸発もあるため、冬場の湿度コントロールが容易だった可能性も高いと考えています。この冬が初めての本格的にこのシステムを動かせるタイミングだと考えているため、様々な状況に対応可能か試していきたいと思います。今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。